給湯温度は何度がいいかご存じですか?
実は、給湯器メーカーで推奨温度は決められています。しかし、ご存じない人も多いようです。
給湯温度は給湯器の寿命にも関わるところです。
そこで今回は、給湯温度について解説していきます。
○この記事のまとめ
- 給湯器の温度設定は50度~60度が好ましい
- ガス代・光熱費を節約するならば、サーモスタット混合水栓を利用した上で50度~60度に給湯温度を設定すべき
○節約術は以下の記事でも特集!
Webで無料相談・見積もりをする
給湯器の温度設定は50度~60度が好ましい | 42度以下が壊れるは根拠なし!

給湯器の温度設定を42度以下に設定した場合に、給湯器本体が壊れやすくなるという因果関係は厳密に示されていません。
但し、給湯器メーカーは温度設定を50度~60度にするよう推奨されています。
給湯器の温度設定を高くすることによって、温度調整がうまくいきやすいからです。
例えば40度のお湯を38度に微調整するよりも、50度のお湯を40度に調整する方が快適な温度を保つことができるということになります。
近年お風呂の水栓で主流となっている「サーモスタット混合水栓」について触れていきます。
サーモスタット混合水栓とは?
→給湯器で沸したお湯に水を混ぜて、蛇口から出てくるお湯の温度(吐水温度)を調整する水栓
サーモスタット混合水栓を使うことにより、給湯器のリモコンで設定した温度よりも吐水温度が低くなります。
例えば給湯器リモコンの設定温度が40度だとすると、サーモスタット混合水栓の温度目盛りが40度でも、吐水温度は40度よりも低い38度や37度に下がります。
■補足①
給水や給湯圧力(水圧)の変化などによっても設定した吐水温度にならない場合があります!
万が一設定温度にならないなど、異常を感じる場合は、こちらも確認してみて下さい。
■補足②
夏期など入水(給水)温度が高い場合には、蛇口から出るお湯の温度が給湯器の設定温度よりも熱いことがあります!詳しくは、こちらをご覧ください。
ガス代・光熱費を節約する給湯器の温度設定方法2選
次に、ガス代・光熱費を節約するための温度設定方法を2つご紹介いたします。

給湯器の温度設定を50度~60度にする
給湯器の温度設定を50度~60度に設定することで、ガス代・光熱費を節約できます。
給湯器から吐水口までに届く温度差が給湯量に関係しているため
理由をもう少し分かりやすく補足すると、給湯器で作られたお湯は、給湯配管を通して吐水口から排出されますが、排出されるまでにお湯の温度は設定温度よりも低くなります。
上述でも触れましたが、給湯器の温度を40度付近で設定した場合、手元にお湯が届いたときには、水の調温の関係でぬるいお湯が吐水されるため、給湯温度を上げざるを得なくなります。
また温度を上げている間はぬるいお湯を出した状態で適温のお湯が排出される状態を待つこととなり、無駄なお湯を流すこと(給湯量の増加)でガスの消費が増加し光熱費がかさんでしまいます。
しかし最初から設定温度を比較的高めで設定した場合は、手元にお湯が届く時点でお湯が適温となって吐水口から排出されるため、お湯の無駄がなくガス光熱費の削減に繋がります。
サーモスタット混合栓を利用する
サーモスタット混合栓を利用することでも、ガス代・光熱費を節約できます。
そもそも、水栓には単水栓・混合水栓の2種類があります。それぞれの仕組みは以下のようになっています。
| 水栓の種類 | 仕組み |
|---|---|
| 単水栓 | 給湯器の設定温度のお湯をそのまま排出する |
| 混合水栓(サーモスタットなど) | 給湯器の設定温度のお湯を混合栓の中で水と混ぜて合わせて混合栓の温度で排出する |
単水栓と混合水栓を比較した場合、サーモスタット機能を有するサーモスタット混合水栓を利用したほうが少ないお湯の量で給湯ができるためガス光熱費削減に繋がります。
サーモスタット混合水栓は水と混ぜることにより、給湯しなけれなばらない水の量が少なくなるからです。
| 水栓の種類 | 仕組み |
|---|---|
| 単水栓 | 給湯器で作られた40度のお湯10Lを直接排出。 |
| サーモスタット混合水栓 | 給湯器で作られたお湯に混合栓内で水と混ぜ合わせてお湯を排出。 理論上 50度のお湯7.8Lに水温5℃の2.2Lの水を混ぜ合わせることで約40度のお湯を排出することができます。 (水2.2L分、少ないお湯の量で給湯が可能) ■参考 異なる温度のお湯と水を混ぜる時の温度計算式 (水温×水量)+(お湯の温度×お湯の量)÷(水量+お湯の量)=お湯の温度 式(5×2.2)+(50×7.8)÷(2.2+7.8)=401÷10=40.1≒40度 |
しかし、給湯器の設定温度は、単水栓では40度、サーモスタット混合水栓では50度であり、その差が10度あります。給湯量は少ないものの、温度差によって本当に光熱費の削減に繋がっているのか疑問を持たれることでしょう。
そのため、給湯温度が異なる場合のガスの消費量を調べる必要があります。
基本的にガスの消費量は、給湯設定温度の上昇に伴い消費量は増加します。この理屈からすると、50℃のお湯を作るためにはガスの消費量が多くなります。
ここがポイント!
お湯の給湯量と給湯設定の温度差を比較して、ガスの消費量を確認しましょう!
ガスの消費量は以下の式で求めることができます。
ガスの消費量(m³)=湯量(L)×温度差(設定温度-水温)÷熱効率(※1)÷ガスの熱量(※2)
※1熱効率 非エコジョーズ0.8
※2ガスの熱量 都市ガス10,750kcal/プロパンガス 24,000kcal
では実際に式にあてはめて比較していきます。
条件:下記①、②共に水温5度、給湯器は非エコジョーズ型、プロパンガスを30日使用
①単水栓で41度(手元に届くまでの温度40度に対して温度減少を考慮した設定温度)のお湯10Lを排出した場合の1ヶ月のガス消費量(m³)
10×(41-5)÷0.8÷24,000=0.01875(m³)/1日
0.01875×30日=0.5625(m³)
②混合水栓で50度のお湯7.8Lを排出した場合の1ヶ月のガス消費量(m³)
7.8×(50-5)÷0.8÷24,000=0.01828(m³)/1日
0.01828×30日=0.5484(m³)
上記①と②の差は
0.5625-0.5484=0.0141(m³)
僅かな差ではありますが、結果として給湯温度を50度に設定したサーモスタット混合水栓を利用したほうがガスの消費量は少なく、すなわち光熱費の削減に繋がることが分かります。
お風呂での電気代・水道代節約術4選

温度設定を低くするにも、節約術は多くあります。
ここでは、お風呂への給湯の際に利用できる節約術をご紹介いたします。
浴槽の湯量を5割にする
つい浴槽の8分目あたりまでお湯をはりがちですが、浴槽は5分目程度のお湯から十分に入浴が可能です。
特に1人暮らしであまり湯量が必要な場合は、浴槽の湯量を5割にしましょう。
給湯の際に、5割程度で止められるようタイマーを設定するとなお良いでしょう。
浴槽はこまめに蓋をする
折角お湯をはったにも関わらず、蓋をしないと冷めるのが早くなります。冷めると追いだきの回数が増えるため、こまめに蓋をしましょう。
また蓋の代わりに市販の「保温シート」を利用するのも有効的です。
入浴時間を揃える
家族でお風呂に入る時間が異なると、お湯が冷めやすくなる傾向にあります。お湯が冷めると、おいだきを使用してしまい光熱費が上がってしまいます。
そのため出来る限り、家族間で入浴時間を揃えてみましょう。
たし湯を活用する
少しお湯がぬるくなってどうしても温めたい場合は、おいだき機能よりもたし湯機能のほうがガスの消費量が少なくて経済的です。
ただしお湯が冷めきってしまった場合は、おいだき機能よりも温めに時間がかかってしまうため不向きであることに留意しておきましょう!
シャワーの使用時間を見直す
シャワーは出しっぱなしにせず、こまめに止めておきましょう!
ちなみに、約17分間のシャワーの使用で浴槽1杯分ののお湯が吐出されます。
節約のためにシャワーのみを利用している方は、それ以上にシャワーの時間が長くならないように使用時間を意識しておく必要があります。
キッチン・台所での電気代・水道代節約術3選

キッチンでもできる電気代・水道代の節約方法をご紹介いたします。
温度設定を低めにする
キッチンでお湯を使用する時は、お風呂よりも温度設定を低めにするといいでしょう。
すこしぬるいくらいでもあまり問題はありません。
お皿は水でつけおき洗い、すすぎでお湯を利用する
お皿につけおきする時は水を利用しましょう。
お湯を使ってしまいがちですが、結局は冷えますしさほど違いはありません。
お湯は水から沸かす
お湯を鍋にためて火にかけても、実は光熱費の削減に繋がりません。
お湯を作るための消費カロリーは火にかける消費カロリーよりも非常に高く、ガスの消費量が増加します。
そのため、水から沸かすほうが経済的です。
給湯器に関するご相談は、お客様満足度97.3%のミズテックまで!

エコキュートへの交換をご検討される際は、ミズテックに是非ご依頼ください!
もし温水給湯器からエコキュートへ切り替えるとしても、交換費用がかさばってしまうと非常に困ります。またエコキュートは業者によっても販売価格はかなり異なります。
少しでもお得に・安心して交換工事を依頼したい場合は、ぜひミズテックへご相談ください。
- メーカーから直仕入れのため最大91%OFFで給湯器を販売
- 工事担当者は全員資格保有の技術者
- 施工後は10年の無償保証付き
交換工事のお見積りは、WEBのお問い合わせフォーム・電話・LINEにて受け付けております。
以下のフォームからも気軽に概算見積ができるため、気軽にお試しください。






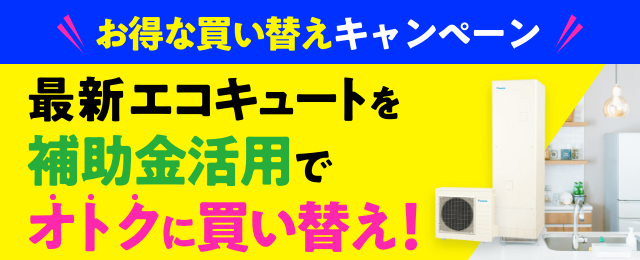














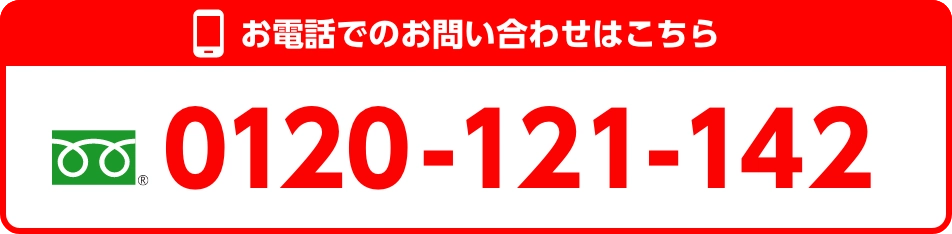

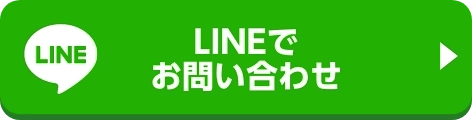

オペレーターより正式な見積を希望しますか?