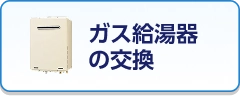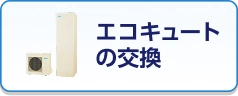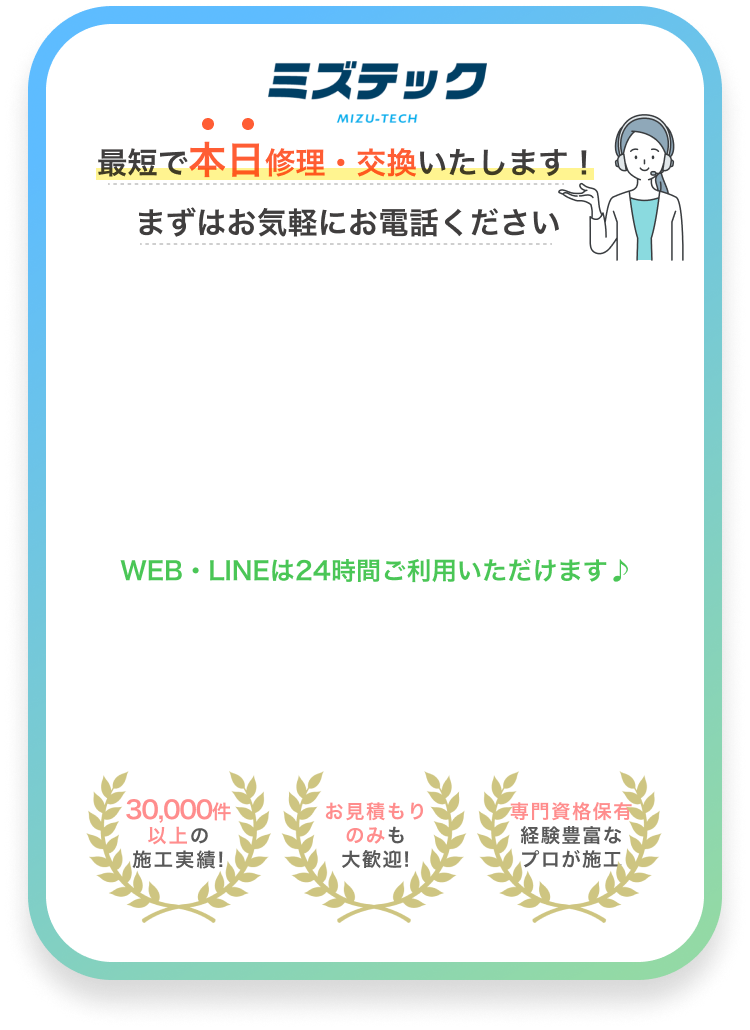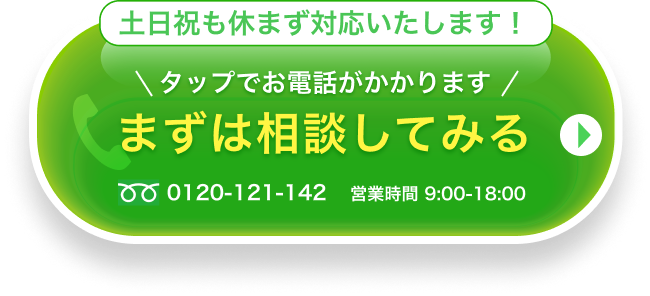「生ゴミ処理機って便利そうだけど、実際の電気代はどれくらいかかるの?」
そんな疑問をお持ちではありませんか?
使い始めてから「思ったより電気代が高い…」なんて後悔は避けたいですよね。
この記事では、生ゴミ処理機の電気代の目安はもちろん、節約するための具体的なコツまでしっかり解説しています。
また、よく比較されるディスポーザーとのランニングコストや使い勝手の違いについても紹介します。
無駄な出費を抑えつつ、自分に合った処理方法を見つけたい方は、ぜひ最後までチェックしてください。
生ゴミ処理機に関して分からないことがあれば、ミズテックへご依頼ください。
目次
生ゴミ処理機の電気代はいくら?

生ゴミ処理機は、本体価格だけでなく継続的にかかるコストにも注意が必要です。
| 項目 | 1回の電気代目安 | 1ヶ月の電気代目安 |
|---|---|---|
| 乾燥式 | 約30〜80円 | 約900〜2,400円 |
| バイオ式 | 約10〜100円 | 約300〜3,000円 |
| ハイブリッド式 | 約20〜40円 | 約600〜1,200円 |
乾燥式は処理時間やモデルによって電気代が変動し、短時間で済むものは安価ですが、長時間稼働する場合は高くなる傾向があります。
バイオ式は手動であれば電気代がかからないものもあります。しかし、自動脱臭機能付きの場合、使用頻度に応じて高くなることがあるでしょう。
ハイブリッド式は乾燥式よりも消費電力が少なく、省エネ設計で比較的安価に運用できます。
乾燥式生ゴミ処理機の電気代
乾燥式生ゴミ処理機は、内部のヒーターで生ゴミの水分を蒸発させて乾燥させる方式です。1回の運転で約30〜80円程度の電気代がかかります。
消費電力は500W~800Wとやや高めですが、生ゴミの体積を大幅に減らし、処理後のゴミは軽量で扱いやすくなります。
処理時間は2~6時間程度と長めですが、臭いや害虫の発生を防ぐ効果も高いのが特徴です。電気代はやや高めでも、手間なく生ゴミを減らしたい方におすすめです。
バイオ式生ゴミ処理機の電気代
バイオ式生ゴミ処理機は、微生物の働きによって生ゴミを自然分解させる方式で、消費電力が少ないのが特徴です。1回あたりの電気代は約10〜100円とばらつきはあります。
消費電力は50W~100W程度で、電気代を気にする方に向いています。処理時間は長めですが、温度管理などで安定的に生ゴミを分解してくれるのです。
バイオ材の補充や定期的なメンテナンスは必要ですが、環境にやさしい処理方法として人気があります。
ハイブリッド式生ゴミ処理機の電気代
ハイブリッド式は、乾燥式とバイオ式の特徴を組み合わせた処理方式です。
乾燥と微生物分解を同時に行うことで、効率よく生ゴミを減量します。電気代は1回あたり約20〜40円と中間的な水準で、消費電力も250W~500W程度です。
処理時間は比較的短く、乾燥だけでは難しい分解処理も可能です。バランスよく電気代と処理能力を重視したい方におすすめのタイプです。
生ゴミ処理機の電気代を節約する方法

生ゴミ処理機は便利ですが、電気代が気になる方も多いはずです。
ここでは生ごみ処理機の電気代を節約する方法を3つ紹介します。
生ゴミの量や水分を減らす
生ゴミの量や水分が多いと、処理機の稼働時間が長くなり、消費電力も増加します。
特に乾燥式の場合、水分が多いと乾燥に時間がかかるため電気代が高くなりがちです。
事前に水切りをしておく、なるべく大きなゴミは細かくするなど、生ゴミの量と水分を減らす工夫をすることで、処理時間短縮と電気代節約が可能です。
電力会社のプランを見直す
電気代全体を見直す方法として、電力会社の料金プラン変更も効果的です。
夜間の電力単価が安いプランや、時間帯によって料金が異なるプランに切り替えれば、生ゴミ処理機を電気代の安い時間帯に稼働させることで節約できます。
乾燥式など電力消費が大きいタイプを使用している場合は、電力会社の見直しが大きな節約につながります。
省エネ設計の生ごみ処理機を選ぶ
最新の生ゴミ処理機の中には、省エネ設計を取り入れている製品も多くあります。
消費電力が低めに抑えられている機種や、短時間で効率的に処理できる機能が搭載されたものを選べば、毎回の電気代が確実に抑えられます。
購入時は「省エネ性能」や「年間電気代目安」などの表示を確認して、長期的なコスト削減を意識して選ぶとよいでしょう。
生ゴミ処理機とディスポーザーの電気代を比較

生ゴミ処理機とディスポーザーはどちらも生ゴミ処理を手軽にしてくれる便利な設備ですが、電気代やランニングコストに違いがあります。
| ディスポーザー | 生ゴミ処理機 | |
|---|---|---|
| 電気代(1回あたり) | 約1~5円 | 約10~30円 |
| 処理スピード | 数秒~数分 | 数時間(2~6時間) |
| ランニングコスト | 低コスト(水道代+電気代) | 電気代やメンテナンス費が必要 |
ディスポーザーは1回あたりの電気代が非常に安く、処理スピードも早いため、長期的に見るとランニングコストが抑えやすいのが特徴です。
電気代をできるだけ節約したい方には、ディスポーザーの方がおすすめです。
生ゴミ処理にディスポーザーを導入するメリット・デメリット

ディスポーザーは便利な反面、注意すべきポイントもあります。
メリットとデメリットを表で比較し、導入前の参考にしてください。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| ・生ゴミの量を減らせる ・ゴミ出しの回数を減らせる ・害虫の発生を抑えられる ・キッチンを清潔に保てる | ・設置工事が必要 ・使い方を誤ると詰まりの原因になる ・作動音が気になる場合がある |
それぞれ詳しく見ていきましょう。
メリット
ディスポーザーには「生ゴミをすぐ処理できる」「キッチンの清潔を保てる」「ゴミの量を減らせる」「手間が減り時短になる」といったメリットがあります。
生ゴミの臭いや虫の発生を防げる点が大きな魅力です。
また、ゴミ出しの回数が減ることで家事の負担も軽減され、忙しい家庭にとっては大きな時短効果があります。
自治体によってはゴミの減量化に貢献できる点でも評価されています。
デメリット
一方で、「排水管の詰まりリスク」「設置できない物件もある」「水道代・電気代がかかる」「一部自治体で使用制限がある」といったデメリットもあります。
集合住宅や賃貸物件ではディスポーザーの設置が許可されていないケースも多いため、事前確認が必要です。
また、使用方法を誤ると排水管が詰まりやすくなるため、正しい使い方を守る必要があります。ランニングコストや自治体のルールにも注意しましょう。
生ゴミ処理にディスポーザーを使用する際の注意点

ディスポーザーは非常に便利な設備ですが、使い方を誤るとトラブルの原因にもなります。
以下の注意点を押さえて、正しく活用しましょう。
水道代がかかる
ディスポーザーは生ゴミを排水と一緒に流すため、処理時に水を流し続ける必要があります。
そのため、生ゴミ処理機と比較すると水道代がかかる点がデメリットとして挙げられます。
しかし、実際の水道代は1回あたり数円程度と微々たるもの。月額で見ても大きな負担にはなりにくいのが特徴です。
それ以上に、生ゴミの悪臭や害虫発生を防げる点は大きなメリット。キッチンを清潔に保てることを考えれば、わずかな水道代以上の価値があると言えるでしょう。
たくさんの生ゴミを一度に処理できない
ディスポーザーには一度に処理できる生ゴミの量に限度があります。
大量の生ゴミを一気に投入すると、排水管の詰まりや内部の故障につながる恐れがあるため注意が必要です。
効果的に使用するためには、生ゴミを少しずつ分けて投入し、処理中は必ず水を流し続けましょう。
また、水の流量が不足すると、排水管内にゴミが残って詰まりやすくなるため、十分な水量を確保して使用しましょう。
正しい使い方を守ることで、長く快適に利用できます。
生ゴミすべてを処理できるわけではない
ディスポーザーは非常に便利ですが、処理できない生ゴミも存在します。
適切に使用するためには、流せるものと流せないものをあらかじめ把握しておきましょう。
以下にそれぞれを表で整理しました。
| 流せるもの | 流せないもの |
|---|---|
| ・野菜くず(葉物・皮など) ・果物の皮(バナナ・リンゴなど) ・ご飯 ・パン ・麺類 ・肉や魚の細かい部分 ・少量の卵の殻 ・柔らかい豆腐 ・豆類 ・小さな魚の骨 | ・貝殻(ホタテ・アサリ・牡蠣など) ・硬い骨(鶏・豚・牛の骨) ・大量の油やラード ・プラスチック ・ビニール ・金属・大量の卵の殻 ・とうもろこしの芯 ・繊維質の強い野菜(セロリ・とうもろこしの皮) |
長く安全に使用するためにも、投入前には、必ず適切に分別・選別し、処理可能なゴミだけを投入しましょう。
生ゴミ処理ができるディスポーザーの導入を検討中ならミズテックへご相談ください

ディスポーザーは生ゴミを簡単に処理でき、キッチンを清潔に保てる便利な設備です。
ただし、ディスポーザーにも地域によっては設置条件がある、処理できないものがあるといった注意点があります。
導入を検討する際は、メリット・デメリットを理解し、ご家庭のライフスタイルに合った製品を選ぶことが重要です。
ミズテックは北海道から大阪まで、幅広いエリアに対応できます。ディスポーザーに関する疑問やお悩みは、ぜひ「ミズテック」までお問い合わせください。快適なキッチン環境づくりを全力でお手伝いいたします!